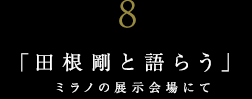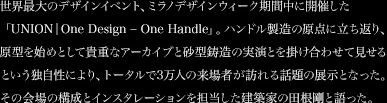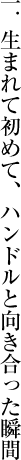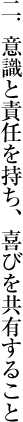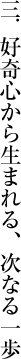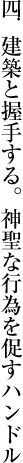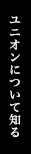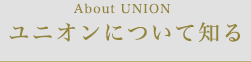会場内を巡っていると展示作品のあいだを気持ち良く通り抜けることできるように感じるのですが、最初の部屋に展示している60点という作品数は、当初から決めていたのでしょうか?
「One Design – One Handle」をコンセプトに、最初の部屋の展示数は、ユニオンの創業60周年に合わせ、60点をセレクトしました。奥の展示室では、初めて生産の現場を見たときの驚きの気持ちをそのままに、金型を用いた大量生産が当然の時代に、一つひとつを砂型で丁寧に成形しています。

薄暗い空間に浮かび上がる60の展示台。床には非常に細かな砂利をシルバーに塗装し、敷き詰めた。
一つひとつがライトアップされているのも印象的です。この照明システムもオリジナルでつくっていただいたものですよね。
プロトタイプ、素材、道具など、それぞれがクローズアップされるように考えました。今回の展示設計で、僕も生まれて初めてハンドルと真正面から向き合ったような気がします。どのような素材があり、どのような工程でデザインを実現していくのか。ディテールをじっくり眺めていると、建築のパーツであるハンドルが、なぜか彫刻のようにも見えてきました。
木製、ガラス製、樹脂製など、さまざまなハンドルが存在しますが、ハンドルづくりの原点といえば鋳物です。会場で製造プロセスを見せている砂型鋳造は、まさしく当社が創業当時から行なっている製法。ユニオンのハンドル作りの歴史がアルミ素材の鋳物から始まり、それが建築の“顔”として存在しうることを、我々自身も再認識することができます。

ハンドルの原型や素材の塊、鋳造のときに使用する道具を、美術品のように整然と陳列している。
ハンドル専門メーカーとしては、ユニオンは日本では先駆者ですよね。これまでにさまざまな建築家、デザイナーとお仕事を重ねてきたと思うのですが、思い出に残っているプロジェクトはありますか?
なんと言っても村野藤吾さんとのプロジェクトですね。難しかったのは、アクリルのなかに真鍮のローレット(細かい凹凸加工が施された金属棒)を閉じ込めてほしいというオーダー。2つの素材が温度により異なる寸法変化をするので、最初は全部割れてしまったんです。しかし、求められるレベルを達成するために、何度も試作を重ねるうちに新たな可能性が見えてきて、現場の実力もどんどんついてくる。あるとき村野さんが設計した大阪・心斎橋にあった喫茶店「プランタン」(現在は閉店)の手すりを担当したときは、工場でつくったものを建物の内部に持ち込み、現場で曲げながら、細かな部分を調整するなんていうこともありました。無理難題とも思える事案が多かったですが、それがユニオンの実力と信頼に結びついたといっても過言ではありません。

独創的な3次曲面を持つ、村野藤吾が1960年に設計を手がけた都ホテル(現在のウェスティン都ホテル京都)のハンドル。
この展示ではハンドルの素材や道具、ものづくりの仕組みの原点にフォーカスしていただきましたが、内部の人間でもこうした基本的な部分を理解しているものが減っていることは否めません。昔は営業の人間も工場に出かけて、製造の担当者や職人と直接打ち合わせをしたものです。時代とともに状況は変わり、専門性や合理性を追求するがあまり、セクションごとに分かれて作業をしているからでしょう。
やりとりのスピードはどんどん速くなり、生産量も圧倒的に増えましたからね。現代では、顔を突き合わせて対話を重ねることよりも、部署ごとに役割を決めて、それぞれがシステマチックに動くことで、手際よく段取ることも求められます

金属の枠が登場する以前に鋳物の現場で用いられていた木枠も展示。
今回の展示を見て、改めてものづくりの現場で何が行われているのか、社員全員が勉強し直し、理解を高める必要があると感じています。
各分野の専門性は必要ですが、その間の行き来がなくなってそれぞれが孤立してしまってはいけません。意識と責任をそれぞれが持ち、「全員でつくりあげたもの」という喜びが共有できる関係になるのがベスト。ものづくりの現場にその感覚がなければ、良い建築も生まれません。

砂型鋳造を繰り返しているうちに、熱で砂はどんどん黒みを増していく。
若い世代を見ていると夢を持って仕事をしている人が少ないように思えますが、田根さんは日本では大きな夢が描けないから海外を拠点にしていらっしゃるんでしょうか?
僕は夢しか持っていません(笑)。海外をベースにしている理由は自然の流れというものありますが、大学2年のときに、ヨーロッパを一人旅したときの衝撃が大きかったですね。そこに過ごす多様な人々。地域ごとの歴史や文化を象徴する重厚な建築物。初めてのものばかりに驚きながらも、自分が見ているものは、まだそのごく一部にすぎない。だからこそ、もっと広い世界を見ながらチャレンジを重ねたいと思ったのです。
先代である僕の父もチャレンジャーで、英語も話せず、飛行機嫌いだったのに40代のときに1ヶ月ほどかけて世界一周をしています。海外の最新の建築物のハンドルを見ながら、自分が手がけている仕事のクオリティの高さを確認し、自信を持ったそうです。当時父が現地の記録をメモしたノートを、いまでも僕はときどき眺めることがあります。父からはとにかく「一流と付き合え」と言われてきました。建築家でも職人でも、一流の人々と付き合うことで感性が養われ、一流のものづくりにつながると。田根さんは、感性をどのように養われたのでしょうか。

時代を切り開いた父の意志を後世に伝えたいと語る立野社長。
なによりも好奇心を持つことを大切にしています。自分の周りにあることに興味を持ち、そこで生まれた内なる感覚を自分のなかに溜め込んできました。そこから新たなものを生み出す力に転化する。僕はチャレンジすることしか考えていないので、自分になにができるのかを問いかけ続けています。情報やモノに溢れている時代だからこそ、いまに満足することなく自分を追い込み、本当に何がしたいのかを深く掘り下げる。不可能なことでも、なぜできないのかを考え、そこから新たに一歩踏み出すからこそ、それが喜びとなり、さらに人を惹きつける未来を作ることができると信じています。

「挑戦の繰り返し」と自身のキャリアを振り返る田根剛。
今回の展示は、僕としても個人のチャレンジの枠を超え、ユニオンの、そして時代の推進力へと変えていくことができるかは重要なポイントでした。ミラノデザインウィークに何トンもの土を持ち込んで、砂型で鋳物をつくる状況を見せることに直接的な意味があるのではなく、それに挑戦することでハンドルの未来が見えてくるかもしれないと思うのです。「ハンドルとは何か」について、考古学的な発掘、科学的な研究を行い、その原点に立ち戻ることで道筋がはっきりし、目指すべき先が見えてくるはず。

「砂型鋳造のプロセスを集中して観察できるように、実験室に見立てた空間をデザイン。
「原点を見ることで、ユニオンの未来をつくっていきましょう」と田根さんに言われたのは、とても印象的でした。もし僕が担当していたら、これまでに手がけた何千ものハンドルを並べて、さらに新しいデザインを発表するという程度に終わり、これほど内容のあるものには結び付けられなかったでしょう。創立60周年という区切りの年に、13年ぶりにミラノで展示をする意味。それはハンドルの美しさを表現することよりも、いかにハンドルやそれにまつわるものづくりが人の心に触れ、新しい気づきにつながるのかを確かめたかった。

日本の職人が繰り出す鋳造の技に、世界各国から訪れた来場者が注目する。
「なぜハンドルが必要なのか」「なぜ生まれたのか」「このデザインにはどんな意味があるのか」。ハンドルを製造する技術が高まった一方で、それぞれの理由を考える工程が抜け落ちてしまった。メーカーだからつくらなければいけない、デザイナーだからデザインしなければいけないという勝手な思い込みばかりが先行し、それを続けた先に何が残るのかわからなくなっていることが多いのです。
ハンドルは手を通して人の心に触れ、そこで過ごす時間や空間の印象にも大きく影響するものですからね。

しっかりと固めた砂型のなかに、「湯」と呼ばれる熱で溶解した金属(会場ではスズを使用)を流し込んでいく。
ドアのハンドルがなければ、建物にだって入れません。建築では空間に触れることはなくても、手すりやドアノブには触れるもの。触れたときの感触が、スペースの良し悪しを決めることもあるでしょう。ハンドルに触れ、扉を開ける瞬間は、建築と握手するようなもので、ある種神聖な行為とも言えるのです。だからこそ、企業の思想を反映した定番を持つメーカーに長年の信頼が寄せられるのかと。
流行は短命に終わりますが、材質や仕上げの本質的な魅力が大きく変わることはありません。時代を超えて愛され、喜ばれるものづくり。そこを私たちも忘れてはいけないと、この会場を見ながら改めて感じています。ガウディのサグラダファミリアや、奈良の法隆寺など、しっかりと考え、作られた建造物には、時代や地域を超えて人を魅了する力がありますからね。

型から取り出したハンドルから砂を払いおとす。縁に残ったバリや湯道などを丁寧に除去したら完成だ。
どれほど長く使われるのか、使ってほしいのか。完成することがゴールではなく、それが使い続けられるビジョンが作り手のなかにあるか否かで、建築の質は大きく変わります。建築の枠組みを超えて生まれた「文化」は、時代を超えて繰り返し新たな価値を創造していくのです。

Photo : Sohei Oya
Writing : Hisahi Ikai